東京都内の銭湯やスーパー銭湯786軒(口コミ2,388件)
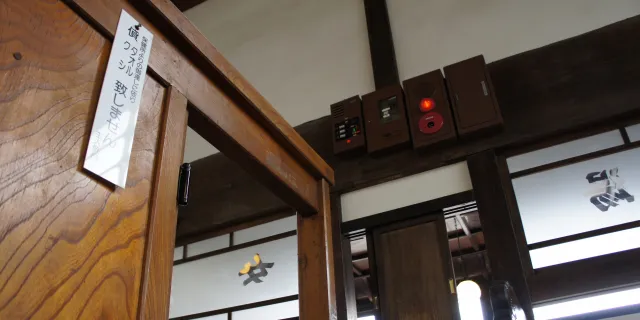
サウナや露天風呂、温泉など大きな湯船で一日を疲れを癒せる東京都内にある銭湯やスーパー銭湯786軒の情報を集めました。「東京都内の地域から探す」では各エリア毎に店舗情報を掲載。「東京都内の路線図から探す」では駅から近い銭湯の情報を一覧で掲載しています。他にも実際に銭湯を利用したお客様の「口コミ」2,388件掲載しています。また東京都内で閉店した銭湯やスーパー銭湯は「196軒」あります。
東京都内の地域から探す
| 東京23区(526) | |
|---|---|
| 多摩北部(48) | |
| 多摩南部(11) | |
| 多摩西部(5) |
東京都内の路線図から探す
| JR線 | |
|---|---|
| 地下鉄線 | |
| 私鉄線 |
銭湯の謎 in 東京

それはやはり外観が宮造りであり、その外観をさらに堂々と豪華に見せるための演出効果であろう。加えて銭湯のもつ極楽浄土性をここでも表現している。それを物語るのが、東京のキングオブ銭湯「大黒湯」(足立区千住寿町)。
昭和4年に造られた堂々たる宮造り様式で、神社仏閣といっても過言ではない。とくに脱衣所の天井は折上格天井で、100枚ほどのそれぞれの升の部分には、花鳥風月の日本画が描かれている。
「梅の湯」(荒川区西尾久)は、昭和26年に新築した際、世界の国旗と犬棒カルタの絵を格天井に揚げた銭湯。子供に文字の勉強をしてもらいたいという、ご主人の意向を反映させたとの事。眺めていると、なんだかほのぼのしていまう空間である。浴場の天井はどうだろう。こちらもやはり、東京型は地方に比べて高い。その高さは平均にして、約8mから10mくらい。
地方の銭湯は、浴室の湯気抜きを天井の中心部に四角い穴を開けた程度なので、高さは必要ない。しかし、東京型の銭湯は、この湯気抜き部分を広く取っているのである。そして、その広さのため屋根に重い瓦を載せることはできず、浴室部分の屋根だけはトタン葺きになっているのも特徴のひとつ。

東京にはお寺や神社のような造りをしている銭湯が多くある。
屋根は「千鳥破風」といい、大きな三角形をしている。その下の入り口には、そりかえったゆるいカーブの「唐破風」が設えてある。これが東京型の定番。この様式が東京の銭湯に取り入れられた時期は大正末期から昭和初期の頃といわれている。
当時、宮大工の技術をもっていた津村亨右さん(故人)は、関東大震災の復興期に初めて、墨田区の銭湯を手がげた。その際に、多くのお客さんを呼べるようにと、自分が持っている宮大工の技術を生かし、玄関入口に唐破風を設け、脱衣所は開放感をもたせるために高い格天井、浴室も大きな湯気抜きの構造を設えるなど、さまざまな工夫をこらした。
もちろんそんな様式の銭湯はどこを探してもないわけで、開店早々たちまち話題を呼び、またたく間に東京中の評判になった。
折しも震災復興期で、新しい銭湯が建ち始めた時期とも重なり、それ以降、建てる銭湯の多くが、宮造り様式となっていった。都内に現存するこのころ建てられた銭湯が、ことのほか豪華である理由は、それぞれの銭湯が競って建物に趣向を凝らしたから。その結果、東京を中心とした関東地方まで、当時は銭湯の定番様式として宮造りは広まり、昭和40年代までその人気は絶えなかった。
しかし、昨今の急激な都市開発の結果、これら宮造りの銭湯はめっきり少なくなってしまい、非常に残念である。ちなみに、震災前の銭湯の様式は、一般の町屋造り風で、いたって単純なものであった。

東京にも温泉の出る銭湯が意外とたくさんある。だから、わざわざ温泉地へ足を運ばなくても、浴場料金で天然温泉が体験できるのだから、これを利用しない手はない。
東京の温泉銭湯の多くは、黒湯と呼ばれるコーラ色のお湯だ。初めて入浴する人は、この色に驚くらしい。この色の正体は太古の時代の植物が変化したヨード分、泥炭や海底の泥、火山灰などが地下水に溶け出したものだという。
温泉の定義は、法で定められた成分(イオウ、重炭酸ソーダなど)を一定の濃度以上含むもの、温度が25度以上のものとされていたが、現在ではこの温度以下でも成分がみたされていれば、温泉として認められるようになった。
この黒湯は、肌がツルツルになるという特徴がある。これはこの湯に含まれるフミン酸という有機分が、肌に皮膜を作り熱の発散を抑制する保温効果が作用しているからだ。そして、おもしろいことにこの黒湯は、都内から神奈川県に行くほど色が濃くなっているという事実もある。
また、この黒湯をもつ銭湯が、京浜急行沿線に集中しているのは、どうやら京浜工業地帯を開発した際、地下水を確保しようとして発見されたためだともいわれている。東京の温泉銭湯は、珍しく貴重な存在なのである。

銭湯のアイテムといえば、あの黄色いケロリン桶が有名である。昭和38年に初めて登場した時は、黄色でなく白色だった。しかし白は汚れが目立つので、後に黄色に変えられていった。
その他、置いてある銭湯は少ないが、女性風呂には、直径が大きく、深さがあり、3本の脚のついた髪洗い専用のケロリン桶もある。また、底にある文字も白ヌキのものや、文字の大きさが違うもの、桶の周囲に赤い線や銭湯名が入っている物もある。
そして、おもしろいことに、東京と関西ではケロリン桶の大きさに違いがあるのだ。
東京型は360グラム、関西型は260グラムの水が入る大きさだ。これは関西人の知恵で、湯を入れすぎないようにする為や、桶いっぱいにお湯を入れると片手では重たくなる。
それについ無駄にお湯を使ってしまうことから、それなら最初から小さい桶にすればいいと、関西人特有の合理的な考えから編み出されたものだ。もっとも、関西に限らず小さいサイズの桶を使用している地域もほかにもあるようだ。
社・日本銭湯文化協会理事・町田忍 著 「銭湯の謎」より
最新の口コミ
2024年11月5日
ぽかぽかランド 鷹番の湯(東京23区 > 目黒)
露店風呂がしっかりしているのが嬉しい
大通りには近いものの直接接していないという好立地。その分場所も広くとれており、露店が楽しめるのが良いです。男女が二階で別れていて時間で入れ替わるので、複数回訪れてどちらがいいのか比較するのも面白いでしょう。また、小さい単位で石けんやタオルを売ってくれているので、忘れ物をしたときも助かりました。
2024年11月5日
永山健康ランド 竹取の湯(多摩南部 > 多摩市)
汗をかきたいならここ
岩盤浴では男女で入ることができるのでカップルや夫婦で来ている人が多い印象です。駅からも近いので立地はわかりやすいと思います。岩盤浴の種類も多く、清潔感もあるので嫌な思いをせず、長居することができます。土日はとても混んでいますが、平日ならゆったりと入ることができてのんびり汗を掻くことができます。お風呂の種類は多くはないですが、岩盤浴で汗をかいた後に浸かるには十分です。
2024年11月5日
極楽湯 多摩センター店(多摩南部 > 多摩市)
ピューロランドで遊んだ後の癒し
駅から徒歩10分ほどの距離で、駐車場もあります。サンリオピューロランドに行って疲れた体を癒すのが最高です。すごく広いわけではないですが、回りやすい広さだと思います。露天風呂もいくつかあり、混雑しがちですが、気持ちがいいので毎回入ります。また、ご飯も美味しくて、家族連れも多いので賑やかで最高です。
2024年11月5日
おふろの王様 多摩百草店(多摩南部 > 多摩市)
いい感じの広さで最高
家からはいつも車で行くのですが、駐車場も余裕があり、早い時間でも遅い時間でも待つことなく入ることができます。温泉はもちろんのこと、漢方蒸風呂が大好きで、行くと大半の時間をそこに費やします。露天風呂も種類がたくさんあるので、蒸風呂であったかくなった後に入ると最高です。
2024年11月5日
RAKU SPA 1010 神田(東京23区 > 千代田区)
サービスが充実していてとても楽しい時間
好きなアニメとコラボしていたことがきっかけで訪れました。お風呂だけでなく、飲食・マッサージ・漫画などいろいろなサービスが揃っており、お風呂に入ってグッズを買って帰るだけのつもりだったはずが、何時間も楽しめました。Raku Spaコースは少々値が張りますが、その分サービスも充実していて楽しかったです。非日常と割り切って時間を過ごせます。館内着もあったのでお風呂の後も濡れとかを気にせずに楽しめました。
東京都内の口コミランキング
- 1位 武蔵小山温泉 清水湯(37件)
- 2位 東京ドーム天然温泉 Spa LaQua(29件)
- 3位 天然温泉 久松湯(28件)
- 4位 ひだまりの泉 萩の湯(20件)
- 5位 南青山 清水湯(20件)
- 6位 おふろの王様 大井町店(18件)
- 7位 戸越銀座温泉(18件)
- 8位 そしがや温泉21(廃業)(18件)
- 9位 燕湯(17件)
- 10位 天神湯(16件)
銭湯・スーパー銭湯検索
北海道・東北
関東地方
東海地方
近畿地方
2024年11月5日
ぽかぽかランド 鷹番の湯(東京23区 > 目黒)
露店風呂がしっかりしているのが嬉しい
大通りには近いものの直接接していないという好立地。その分場所も広くとれており、露店が楽しめるのが良いです。男女が二階で別れていて時間で入れ替わるので、複数回訪れてどちらがいいのか比較するのも面白いでしょう。また、小さい単位で石けんやタオルを売ってくれているので、忘れ物をしたときも助かりました。
2024年11月5日
永山健康ランド 竹取の湯(多摩南部 > 多摩市)
汗をかきたいならここ
岩盤浴では男女で入ることができるのでカップルや夫婦で来ている人が多い印象です。駅からも近いので立地はわかりやすいと思います。岩盤浴の種類も多く、清潔感もあるので嫌な思いをせず、長居することができます。土日はとても混んでいますが、平日ならゆったりと入ることができてのんびり汗を掻くことができます。お風呂の種類は多くはないですが、岩盤浴で汗をかいた後に浸かるには十分です。
2024年11月5日
極楽湯 多摩センター店(多摩南部 > 多摩市)
ピューロランドで遊んだ後の癒し
駅から徒歩10分ほどの距離で、駐車場もあります。サンリオピューロランドに行って疲れた体を癒すのが最高です。すごく広いわけではないですが、回りやすい広さだと思います。露天風呂もいくつかあり、混雑しがちですが、気持ちがいいので毎回入ります。また、ご飯も美味しくて、家族連れも多いので賑やかで最高です。
2024年11月5日
おふろの王様 多摩百草店(多摩南部 > 多摩市)
いい感じの広さで最高
家からはいつも車で行くのですが、駐車場も余裕があり、早い時間でも遅い時間でも待つことなく入ることができます。温泉はもちろんのこと、漢方蒸風呂が大好きで、行くと大半の時間をそこに費やします。露天風呂も種類がたくさんあるので、蒸風呂であったかくなった後に入ると最高です。
2024年11月5日
RAKU SPA 1010 神田(東京23区 > 千代田区)
サービスが充実していてとても楽しい時間
好きなアニメとコラボしていたことがきっかけで訪れました。お風呂だけでなく、飲食・マッサージ・漫画などいろいろなサービスが揃っており、お風呂に入ってグッズを買って帰るだけのつもりだったはずが、何時間も楽しめました。Raku Spaコースは少々値が張りますが、その分サービスも充実していて楽しかったです。非日常と割り切って時間を過ごせます。館内着もあったのでお風呂の後も濡れとかを気にせずに楽しめました。
- 1位 武蔵小山温泉 清水湯(37件)
- 2位 東京ドーム天然温泉 Spa LaQua(29件)
- 3位 天然温泉 久松湯(28件)
- 4位 ひだまりの泉 萩の湯(20件)
- 5位 南青山 清水湯(20件)
- 6位 おふろの王様 大井町店(18件)
- 7位 戸越銀座温泉(18件)
- 8位 そしがや温泉21(廃業)(18件)
- 9位 燕湯(17件)
- 10位 天神湯(16件)
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東地方 | 東海地方 |
| 近畿地方 |